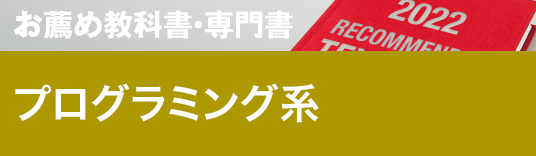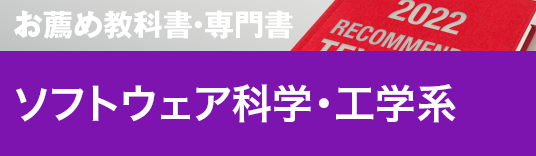近代科学社 お薦め教科書・専門書 2022 専門書
専門書
-
情報処理技術遺産とパイオニアたち
本書は、情報処理学会60周年記念事業の一環として企画された。第一部『情報処理技術遺産』と第二部『オーラルヒストリー』の二部構成となっている。
第一部では、コンピュータ技術の発展の歴史を示す具体的事物・資料であることを認定する『情報処理技術遺産』において、2008年~2019年間に認定された各遺産の情報108件、分散コンピュータ博物館10件を収載している。
第二部では、日本の情報処理技術に多大な影響を与えたパイオニアたち23名を紹介する連載記事「古機巡礼/二進伝心:オーラルヒストリー」を再編している。
本書は、我が国のコンピュータ関連の歴史を紐解く上でも重要なレガシーとして位置づけられる。情報処理分野に携わる方々にとって手元に置いておくべき、高価値な一冊。 -
ロボット制御学ハンドブック
日本では従来からロボットの研究開発が盛んであったが、その進歩は、ともすれば部品や材料・機械設計・コンピュータソフトによるものと捉えられ、ロボットに必須の「制御技術」が見逃されがちである。
そこで、ロボットを思いどおりに動かすために必要な制御技術を知り、ロボットを使えるようにするために、ロボットの制御に特化した領域を「ロボット制御学」と名づけ、実際に、研究・開発に従事している約210名の著者が、なぜロボットに制御が必要なのか? から始まり、モデリング→設計→実装まで一連の流れを理解し、実践できるようになることを目的にまとめ上げた。その範囲は,一般的なロボットの範疇を超え,農作業支援、建築・土木作業支援、健康・介護・リハビリ支援、医療支援、災害対応支援、宇宙開発支援にまでおよぶ。
まさに、ロボット技術を実用化しようとしている研究・開発・利用技術者には、必携のハンドブックである。 -
AI事典第3版
編著者に現在、人工知能研究を牽引する代表的な研究者にご就任いただき、研究の最前線で活躍されている100余名の気鋭の研究者が執筆。
「各執筆者の主観を軸に執筆する。読者が興味を持って面白く読める内容とする。」ことをコンセプトとし、AIにおける論争、汎用人工知能など、新しいテーマも積極的に取り上げている。
今やAIは、様々な研究の根幹をなしており、係わる分野も多岐にわたる。AI研究者はもちろん、工学、理学、医学、薬学、農学、社会、哲学等すべての分野の方々にとって必携の書である。 -
浅田稔のAI研究道
ビッグデータやIoTなども巻き込んで発展し続ける人工知能研究は今後、社会にどう受け入れられていくか? その鍵について著者は、社会システムを構成する人工物に「心的機能」が備わることと説き、それを「ココロの創成課題」と呼ぶ。
本書は、その課題の実現を目指して研究を行ってきた著者の人工知能研究の足跡(動画像処理・強化学習・身体性・情動・共感)をたどりながら、ロボカップ研究(認知発達ロボティクス)から導き出された認知の問題意識などの重要性と成果、そして課題を解説する。
各分野のキーパーソンとの対話やその知見なども紹介。 -
プロジェクション・サイエンス
認知科学は第一世代:記号操作(1970~1990)、第二世代:身体性(1990~2010)の研究を辿り、それらの盲点をカバーしたプロジェクション・サイエンス研究が第三世代として展開され始めている。本書は学術誌『認知科学』のプロジェクション・サイエンス特集に大幅加筆し、再編集したものである。
人は世界から情報を受容し、それを世界へ投射=プロジェクションすることで独自の意味世界を構築している。この作用によって愛着、信仰、幻覚、フェティシズムなど人固有の心理現象が生まれる。心理学だけでなくAIやVRなどの情報科学、社会学や経営学分野の方々にも強く関連する研究といえる。本書では様々な場面における心と世界の関わりを詳細に解説している。
※本書は学術誌『認知科学』(Vol. 26 No. 1 2019年3月)特集『特集−プロジェクション科学』の内容に大幅加筆し、書き下ろし原稿を加えて再編集されたものである。 -
マインドインタラクション
第3次AIブームが起こり、AIの本格的なビジネス利用が始まった。
では、今後の社会でAIはどう使われていくだろうか? 290
本書では、マインドをもつよう設計されたAIが、人間とマインドを通い合わせるマインドインタラクション時代の到来を予測している。
ユーザの意図をくみ取って先に行動してくれる「忖度するAI」、会話の邪魔をしないよう配慮する「空気を読むロボット」…そんな人とAIが共生する社会展望を、人工知能学会前会長と日本認知科学会の気鋭の研究者が、自身の研究成果を交えてわかりやすく解説した。
脚注では様々な用語や筆者らの見解を丁寧に説明し、専門知識不要でも読める1冊に仕上がっている。 -
裏側から視るAI
本書は著者が所属する理研・革新知能総合研究センター 社会における人工知能研究グループの成果をもとに、AI の負の側面の紹介とAI設計・運用における倫理指針を示す構成となっている。第1章ではシンギュラリティ―AIが人間を超える可能性、第2章ではAIに奪われる仕事の範囲、第3章ではAIの発展の歴史、第4章では現状の「弱いAI」がもたらす数々の問題、第5章ではAI倫理を主軸とした社会制度の対応策について解説している。
AI技術に関する記述は基礎に留めつつ、人間社会におけるAIの影響という観点から書かれているため、社会学や社会工学の読者にも大変関心の高い内容である。 -
知能はどこから生まれるのか?
AIが注目を集め、人間を超える人工物の開発が目指されている今日この頃。しかし実は、自然界には脳がなくても賢くふるまう生き物がたくさんいる。いったい、どういうことなのだろうか!?
著者は専門である制御工学の研究を通じ、「知能の源は、環境との相互作用にあるのでは?」という仮説に至った。そして、「現象学」という哲学思想を取り入れて論拠を固め、さらに、生き物っぽく動く「ムカデロボット」を作り、その実証を試みる。本書は、その軌跡の記録である。
わかりやすく親しみやすい文体は、思わず次の頁をめくらせる。また、ところどころにQRコードを配し、手軽に動画を見られるよう工夫した。
人工知能、知能、制御に関心のある読者はもちろん、現象学に関心のある読者にも、お勧めの1冊である。 -
Pythonと複雑ネットワーク分析
本書はまずデータ分析に役立つPythonツールを解説し、経済システムの分析、コミュニティの効率的抽出、口コミ影響力の解析といった内容に続く。
複雑ネットワークはAI技術だけで解決できる分野ではなく、研究の重要性は年々上がっている。Web系のマーケターやデータ分析エンジニア、データサイエンティストや同分野を目指す学生に最適の書である。 -
データサイエンスの作法
データサイエンスの社会的需要が高まる中、データサイエンティストにはデータを的確に把握する能力が求められる。
そのためには、データ全体をさまざまな角度から丹念に調べ理解することから始めなければいけない。
本書ではデータの形式や属性、型などの骨子を解説し、データを扱う上で抑えるべき基本についても著者が開発した視覚表示ソフトウェア「TRAD」(無償)を通して自然に身に着くよう組み立てられている。
20年以上に渡り「サイエンスとしてのデータサイエンス」を追い求めてきた著者が贈る、データの時代に迷わないための必読書。 -
はっきりわかるデータサイエンスと機械学習
AIの要である機械学習は、結果を導き出す過程がブラックボックス化する問題があり、AI実用化の障害となっている。その解決策として、丹念なデータ分析によりデータの背景にある現象を統計モデルで表現する、本来の意味での「データサイエンス」の活用が期待されている。メカニズムが理解可能なモデルをAIの頭脳に使うことで、AIの透明化――すなわち説明可能なXAIも実現できる!
本書ではデータサイエンスの考えに基づく統計モデリングの解説に加え、機械学習の代表的な手法を Rを用いて体験していく。本書を読み込めば、探索的データ解析と機械学習、それぞれの本質を学ぶことができる。 -
スマートモビリティ革命
今,世界では自動運転も含めた人やモノの移動をめぐるモビリティ革命が起きている.なかでも有名なのがMaaS(マース)と呼ばれる「移動のサービス化」である.米国発のライドシェアのUberや,ヘルシンキのWhimがとくに有名である.
一方,日本でも1990年代からITS(高度道路交通システム)と呼ばれる道路交通の最適化を図る取組みが進められてきた.
本書は,現在のモビリティ革命の背景にある世界の公共交通政策や情報技術の進化について概説するとともに,交通・移動サービスに最先端のAI技術を導入した,日本発の「未来型AI公共交通サービスSAVS(Smart Access Vehicle Service)」について,その技術と社会実装の現状を紹介する. -
セジウィック:アルゴリズムC 第1~4部
本書は、2004年に刊行した『アルゴリズムC 新版』の復刊である。
セジウィックの『アルゴリズム』は、世界の標準教科書として大変高い評価を得ている。直感的でわかりやすい説明、アルゴリズムの振舞いを示す数多くの見事な図、簡潔で具体的なコード、最新の研究成果に基づく実用的アルゴリズムの選択、難解な理論的結果のほどよい説明などがその特長である。アルゴリズムに係わる研究者、技術者、大学院生、学生必携必読の書である。
また、続刊『第5部グラフアルゴリズム』の刊行も決定! -
セジウィック:アルゴリズムC 第5部
本書は『セジウィック:アルゴリズムC 第1~4部』に続く,第5部の日本語版.グラフは,現実の問題をコンピュータで計算できるよう離散的な数学モデルに落とし込むための概念であり,本書は,その基礎として外せない項目を網羅している.また、グラフを現実的な時間で解くためのアルゴリズムを豊富に掲載しており,アルゴリズム研究の入門書としてもうってつけである.原著は,『アルゴリズムイントロダクション』と並び称される世界的名著.様々な分野でグラフおよびグラフアルゴリズムの知識が求められている今,待望の翻訳書といえる. -
アルゴリズムイントロダクション 第3版 総合版
原著は,計算機科学の基礎分野で世界的に著名な4人の専門家がMITでの教育用に著した計算機アルゴリズム論の包括的テキストであり,その第3版.前版までで既にアルゴリズムとデータ構造に関する世界標準教科書としての地位を確立しているが,より良い教科書を目指して再び全面的な記述の見直しがなされ,それを基に新たな章や節の追加なども含めて,大幅な改訂がなされている.
単にアルゴリズムをわかりやすく解説するだけでなく,最終的なアルゴリズム設計に至るまでに,どのような概念が必要で,それがどのように解析に裏打ちされているのかを科学的に詳述している.
さらに各節末には練習問題(全957題)が,また章末にも多様なレベルの問題が多数配置されており(全158題),学部や大学院の講義用教科書として,また技術系専門家のハンドブックあるいはアルゴリズム大事典としても活用できる.
本書は,原著の第1~35章,および付録A~Dまでの完訳総合版である.また巻末の索引も圧巻で,和(英)‐英(和)という構成により,「数理用語辞典」としてもまことに有用である. -
世界標準MIT教科書 ストラング:計算理工学
この本は工学と理学の学部学生を対象として,応用数学や計算数学の立場から,研究から開発まで一生涯携わっていく仕事の基礎となる事項について非常に興味深くかつ体系的に導入を行っている教科書あるいは参考書である.
理工学を学ぶには,物理あるいは数学を中心として,すべてを見渡す方法があるが,本書は計算の数理を中心として理工学全般を学ぶのに適している.
著者のストラング教授は優れた研究業績に加えて,MIT において非常によく準備されて学生に分かり易く非常に充実した講義をすることで有名である.
本書も,読み始めると息もつかせぬ程面白いと感じさせる迫力があり,その力で理工学全般の考え方を道案内している. -
世界標準MIT教科書 ストラング 微分方程式と線形代数
MITの名物教授ストラング先生の最新書籍の邦訳である。大学数学の基本である微分方程式、線形代数を、今までのセオリー通り独立して学ぶことはもちろん、交互にどのように関連付いているのかを、具体的事例を提示しつつ基礎から学べるよう工夫してある。また、実際に利用する際にどのように考えればよいかを記述しているので、工学を学ぶ読者にも大変適している。ストラング先生の独特の口調は、教室で講義を受けていると思わず錯覚してしまうほど雄弁である。
微分方程式、線形代数を、研究・開発の基盤におく技術者・研究者や、学部生、大学院生、大学院入試に臨む学生には、必携の書である。 -
新訂版 数学用語 英和辞典
本書は,2013年に刊行した『数学用語 英和辞典』の増補版である.いま社会的に必要とされている統計学やデータサイエンス系の用語を大幅に追加し,全体では数学・数学史・数学教育・応用数学・情報/離散数学・統計学・保険数学・経済数学などの分野で用いられる数学用語を網羅した.また,数学者を中心とする著名学者についても,現役のキーパーソンまで含めて総計千百名以上を掲載.さらに,新たに英-和見出しを反転させた和-英索引を付け,日本語から数学用語を引くことも可能にした. -
離散幾何学フロンティア
数学伝道師、秋山仁先生の離散幾何学の書である。
「離散幾何学」は、離散数学(グラフ理論、組合せ論など)をはじめ、物質設計、数理ゲーム、パズル、さらには芸術作品に至るまで、広い応用があることで知られている。
本書は著者の業績である、タイル張りや変身図形の設計技術を様々な数学的アイデアによって展開し、新しい理論(定理とその証明)が作られていくプロセスや、具体的な応用を示している。独自に考案・発見した多数の離散幾何学の定理を約1、000点におよぶ図版を用いて詳細に述べられている。また、読者が学習しやすいよう章末に練習問題等を配している。 -
現代暗号の誕生と発展
本書は、40年余り前に誕生してから現在に至るまで大きく発展し続けている現代暗号の世界を(前提知識を必要としないで)できるだけ平易に解説する。本文では、極力数式等は用いずに解説を行う一方、いくつかの重要な技術については、より詳細な説明を付録で行っている。現代暗号に関心はあるが、その敷居の高さゆえに躊躇していた読者には最良の一冊である。 -
大学数学のお作法と無作法
数学はなぜ難しいのか? それは「お作法」が分かっていないからだ! 本書は、学部1年生レベルを持ち、数学が不得意で勉強する意味が分からないという方々のための“お作法本”である。その対極にある「無作法」も紹介し、読者を数学の世界へと誘っていく。 -
新 企業の研究者をめざす皆さんへ
前書から十年の間に筆者が経験した、東京大学での技術リーダーシップ講義、統計数理研究所での知見、注目企業プリファードネットワークスの企業文化、政府関係の委員会や学会で得た情報を加えて内容をさらに充実。
前書の日本IBM時代のレター解説だけでなく、筆者が講義で使用したケース事例、ブログや学会誌に寄稿したエッセイも紹介。
研究の方法、論文の作法、キャリア、マネジメント、知財問題など、研究職を希望する学部生や修士・博士課程の学生にとって興味を引く情報が揃い、現役の企業研究者・技術者にとっても読みごたえのある一冊である。 -
23の先端事例がつなぐ計算科学のフロンティア
計算科学とは、数学的モデルとその定量的評価法を構築して今までの難課題を、コンピュータを駆使して解決しようとする新しい学問分野である。
本書は2018年に「産業界の難課題の解決パラダイムを提案する」をキーコンセプトとした理研のシンポジウムを書籍化したものである。専門領域で実際に使われている計算や数式を織り交ぜながら展開するが、学部3年生でも分かるレベルで各分野について具体的に解説する。
データサイエンスやインフォマティクス分野に関心のある読者にも勧めたい書籍である。 -
UX原論
UXという言葉が生まれてからもう20年ほどになるが,いまでは典型的な“バズワード”となっている.すなわち,その概念と方法論については様々なものが混在し,相互の関係も明確にならないまま拡散している状況にある.本書は,この分野の第一人者である著者が,混迷しているUXについて,;歴史的経緯,ロジカルに正しいと考える概念や内容を整理し,その方法論などを解説する.UX従事者およびこの分野に関心のある読者必読の書である. -
高齢者のためのユーザインタフェースデザイン
高齢化が急速に進む日本。本書は、高齢者が直面するUI(ユーザインタフェース)上の問題を洗い出し、高齢者の身体的・認知的特性について解説をおこない,それらに対応するための具体的なデザイン事例を紹介している.
良いデザインだけでなく悪いデザインを取り上げることで,多くの気づきを読者に提示する.本書を読めば,なぜあの製品やこのサービスのデザインがふさわしくないかが見えてくる.産業界のデザイナー必読の書! -
量子探索
本書は量子ウォークを用いる探索問題について,基礎的事項から具体的計算まで丁寧に解説する.
量子ウォークとは確率論におけるランダムウォークの量子版である.従来のランダムウォークでは見られない特異な挙動を示すことから最先端の研究対象として注目を集めている.また,その探索アルゴリズムは,量子コンピュータにも応用可能とされ大変注目されている.量子系の計算科学に関心のある多分野の読者必携の書である. -
Orange Data Miningではじめるマテリアルズインフォマティクス
物質科学・化学工学の研究開発に変革をもたらす技術として「マテリアルズインフォマティクス」が期待され、各分野でその取り組みが急速に進んでいる。
しかし機械学習を用いたデータマイニングである性質上、まずはプログラミング技術を習得しなければいけない実情がある。
本書ではGUIベースのフリーソフト「Orange Date Mining」を使用し、プログラミングを学んでいない人でも機械学習を実践する手法を紹介している。
著者によるサンプルスクリプトとデータファイルも準備しているため、手を動かし理解しながら読み進めることができる。
また各章の練習問題を解けば技術がより身につく構成となっている。マテリアルズインフォマティクスをこれから始める方に最適の一冊。 -
実践 マテリアルズインフォマティクス
化学分野の材料開発はこれまで経験と勘に裏打ちされた実験的手法が中心的な役割を果たしてきたが、新物質の発見から実用化までに長い時間とコストを要している。そこで近年では蓄積された多くのデータ・情報を駆使して所望の構造・材料候補を導き出すデータ駆動型科学――マテリアルズインフォマティクスの活用が始まっている。本書ではマテリアルズインフォマティクスを実践するための機械学習法、実験計画法、記述子計算を詳述。プログラムに必要なPythonとGoogle CoLabについても導入から解説している。これからデータ解析に取り組もうと考えている化学分野の方々にとって指南書となる一冊。
なお、本文中のプログラムソースは、著者のWebサイト等でダウロードできる。
『現代数学ゼミナール』
創立60周年を記念して品切本を無くし、全巻購入いただけます!
近代科学社はこれからも、可能な限り品切れを無くしてまいります
※復刊をご希望の書籍がございましたらご連絡ください。可能な限りお応え致します
シリーズ:『現代数学ゼミナール』
-
線型代数学
-
微分積分学
-
トポロジー
-
入門線形代数
-
半分配環論入門
-
不等式への招待
-
非線形関数解析学
-
集合と位相
-
数学概論
-
統計数学
-
関数解析の基礎
-
現代解析学入門
-
常微分方程式要論
-
調和積分論
-
複素解析学
-
代数学
-
確率と確率過程